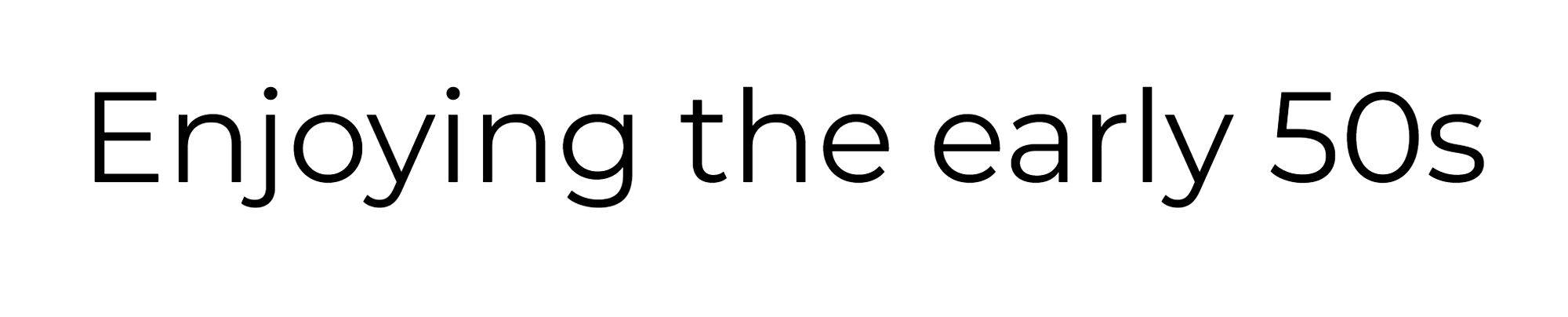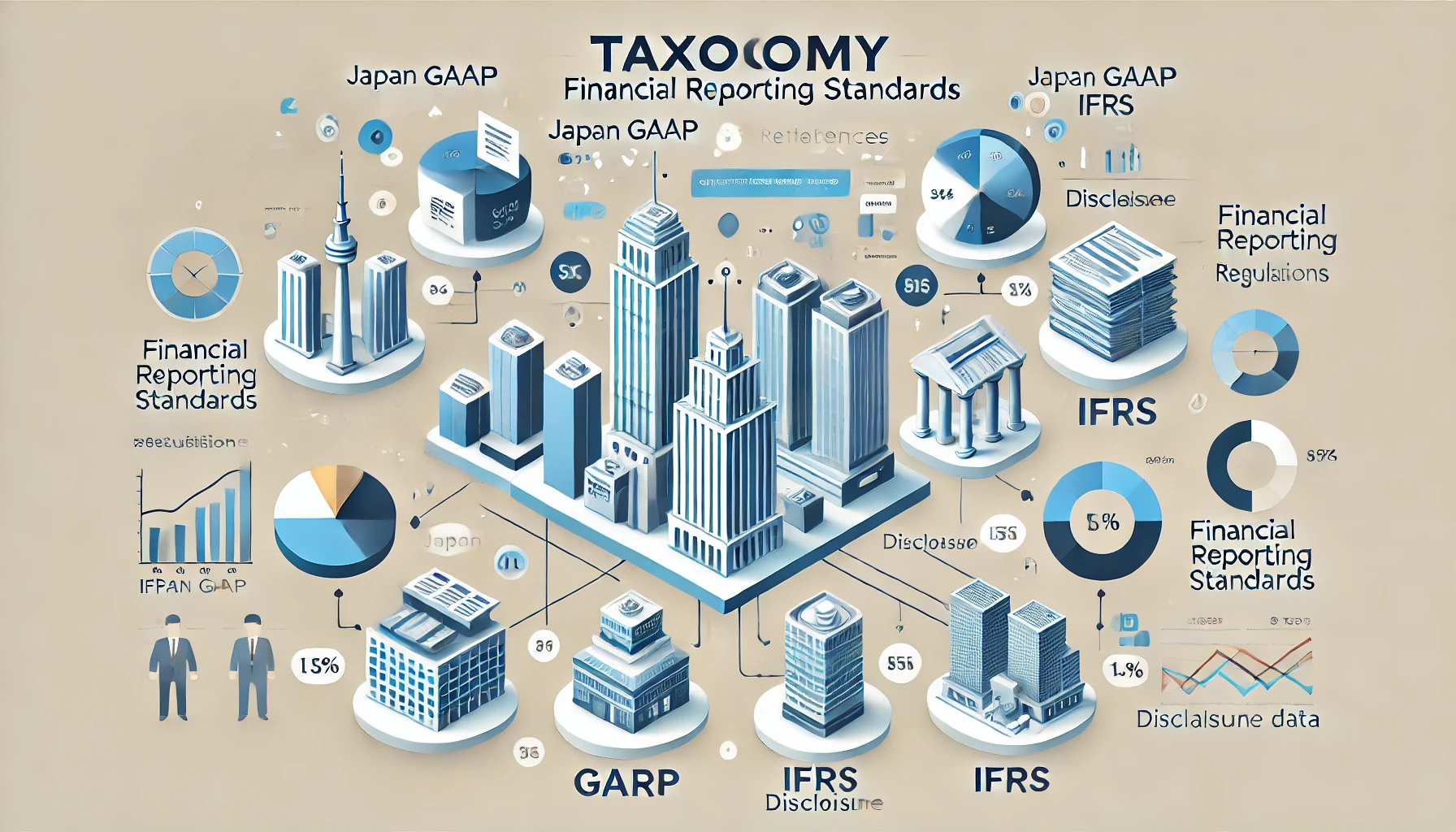はじめに
金融庁が公開している「勘定科目リスト」は、企業が EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork) に提出する有価証券報告書等の 財務諸表(本表) で使用される勘定科目(財務項目)をまとめたものです。
EDINETではXBRL形式により財務諸表等をタグ付けして提出するため、このリストに掲載された各科目はEDINETタクソノミー上の特定のXBRL要素(コンセプト)に対応しています。
以下では、
- 有価証券報告書における勘定科目の具体的な使用例
- XBRLファイル内でのタグ付け方法
- タクソノミー上の構造や会計基準との関係
について解説します。
EDINET提出書類における勘定科目の使用例
上場企業がEDINETに提出する有価証券報告書(年次報告書)では、貸借対照表や損益計算書などの数値データが勘定科目ごとのXBRL要素でタグ付けされています。
例えば、貸借対照表の「現金及び預金」の金額は、EDINETタクソノミーで定義された CashAndDeposits という要素でタグ付けされます。参考: qiita.com
実際のインスタンス(XBRLデータ)では、以下のようなタグが埋め込まれます(インラインXBRLの場合はHTML内に埋込まれます)。
<jppfs_cor:CashAndDeposits contextRef="CurrentYearInstant" unitRef="JPY" decimals="-6">
95111000000
</jppfs_cor:CashAndDeposits>
jppfs_cor:CashAndDepositsは「現金及び預金」を表すXBRL要素。95111000000はタグ付けされた数値(金額)。contextRef="CurrentYearInstant"は当期末時点の連結残高。unitRef="JPY"は通貨単位(日本円)。decimals="-6"は表示精度(百万円単位)。
なお、非連結(単体)財務諸表の値をタグ付けする場合、NonConsolidatedMemberを指定して区別します。
このように企業間で勘定科目名称が異なっていても、共通のタクソノミー要素を用いるため、比較可能なデータとして取得・分析が可能になります。参考: qiita.com
勘定科目のXBRLタクソノミー上の定義とタグ付け方法
勘定科目リストの各項目は、EDINETタクソノミー上でユニークな要素名(コンセプト名)と定義を持っています。要素名は通常英語で、日本語科目名はラベルとして定義されています。参考: 日本公認会計士協会
例えば「現金及び預金」はjpfr-t-cte_CashAndDepositsという名称で、データ型は貨幣金額(monetaryItemType)、期間属性は時点(瞬時項目)です。
タクソノミー上では、
- 勘定科目要素間の階層構造
- 計算関係(総資産 = 流動資産 + 固定資産など)
が規定され、各科目の関係が明確化されています。参考: time2log.com
表示順序や科目の親子関係はプレゼンテーションリンクで階層ツリーとして定義されています。
例えば、
- 流動資産
- 現金及び預金
という階層が定義されています。金融庁資料参照
企業がタクソノミー拡張で独自科目を追加する場合も、この階層ツリーに沿って位置付けを決定します。
金融庁の「報告項目及び勘定科目の取扱いガイドライン」では、タクソノミー拡張時のルールが示されています。金融庁資料参照
また、EDINETタクソノミーではXBRLの「ディメンション(dimensions)」も導入されています。これはセグメント情報や注記の内訳表など多次元的な表現に用いられ、非連結財務諸表にはNonConsolidatedMemberが付加されます。参考: qiita.com
EDINETタクソノミーの構成と各タクソノミーの役割
EDINETタクソノミーは日本の開示制度に対応するため、以下のように構成されています。
- 財務諸表本表タクソノミー (prefix: jppfs)
- 日本基準(日本GAAP)に基づく財務諸表の主要科目を定義
- 国際会計基準タクソノミー (prefix: jpigp)
- IFRSに基づく財務諸表の主要科目を定義
- 開示府令タクソノミー (prefix: jpcrp)
- 有価証券報告書や四半期報告書の本文、注記、非数値情報を定義
日本基準とIFRSのタクソノミーの違い
日本基準とIFRSのタクソノミーは類似した構造を持ちつつ、科目名や定義に違いがあります。
- 日本基準 (jppfs)
- 例:「現金及び預金 (CashAndDeposits)」
- 特有科目:「経常利益」「営業外収益」など
- IFRS (jpigp)
- 例:「現金及び現金同等物 (Cash and Cash Equivalents)」
- 基本的にIFRS公式タクソノミーに準拠
これらはそれぞれ適用される企業が異なり、用途に応じて明確に使い分けされています。
開示府令タクソノミー(jpcrp)の役割
開示府令タクソノミーは財務諸表以外の情報をカバーし、以下の項目を含みます。
- 事業内容
- リスク情報
- 従業員数
- 事業の概況
XBRLインスタンスにおける名前空間の使用例
XBRLインスタンスには複数のタクソノミーから要素が使用されます。
例:
jppfs_cor:CashAndDeposits
ここでのプレフィックスjppfs_corは財務諸表本表タクソノミー(企業共通部分)を示しています。
業種別タクソノミー(事業コード)
日本基準タクソノミー(jppfs)には業種別の細分化があり、事業コードによって識別されています。
- 一般商工業(製造業・サービス業等): cai
- 建設業: cns
- 銀行業(特定取引勘定を持たない): bk1
- 銀行業(特定取引勘定設置銀行): bk2
- 証券業: sec
- 生命保険業: in1
- 損害保険業: in2
- 鉄道業・電気通信業・電気事業・ガス業など: rwy, elc, ele, gas
- 学校法人・社会医療法人: edu, med
企業は提出する有価証券報告書に業種に応じたタクソノミーを選択して使用します。
タクソノミーにおける業種ごとの科目表記の違い
同じXBRL要素でも業種ごとに標準ラベル(表示名)が異なる場合があります。
例:
- 一般商工業: 「現金及び預金」
- 証券業: 「現金・預金」
- 建設業: 「現金預金」
これらはXBRL要素としては同一であり、分析上は同じデータ項目として取り扱われます。
おわりに
金融庁公表の勘定科目リストは、EDINETタクソノミーの要素として定義され、企業の報告や分析の基盤となっています。日本基準とIFRSの違いや業種ごとの相違にも柔軟に対応し、拡張性も備えています。
参考資料
- 金融庁「2022年版EDINETタクソノミの公表について」(令和3年11月9日)
- EDINETタクソノミー概要説明(金融庁、令和3年11月)
- 日本公認会計士協会「新EDINETの概要とXBRLデータに関する監査人の留意事項」(IT委員会研究報告第44号、2014年)
- Qiita記事「よく分からないXBRLをざっくり理解したい男たち!!」(2020年)
- time2logブログ「EDINETのXBRL開発で不可欠なタクソノミの理解と活用法」(2024年)
- EDINET提出者向けガイドライン(報告書インスタンス作成ガイドライン等)